
MUFG Startup Summitの詳細はこちら!
三菱UFJフィナンシャル・グループは、スタートアップ戦略部を新たに設立。銀行のほか、証券や信託、ベンチャーキャピタル(※)各社のグループの司令塔としての役割を果たす。三菱UFJフィナンシャル・グループらしさを前面に出し、顔が見える支援へ。
(※)スタートアップをはじめとした未上場の企業に対して投資を専門とする投資会社や組織のこと
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)がスタートアップ支援を本格化させている。2024年4月から、三菱UFJ銀行に属していた成長産業支援室をバージョンアップするかたちで、グループ持株会社の所属も兼務するグループ横断組織のスタートアップ戦略部を新設。その初代部長に就いたのが、塚原 伸介氏だ。組織を改編する狙いはどこにあるのだろうか。
「今後の日本の産業発展と社会課題の解決を担っていくのがスタートアップであり、そこに日本再興のカギがあると考えています。今年4月からグループの新中期経営計画も始まり、そのなかの重要施策としてスタートアップ支援が採り上げられています。私たちも本腰を入れて、グループ一丸となってスタートアップ支援に取り組みたいと考えているのです」(塚原氏)
新たに設立されたスタートアップ戦略部。銀行と持株会社の所属を兼務するということは、どういった意味を持つのか。
「銀行の組織だけでなく、グループの証券、信託、VC(ベンチャーキャピタル)、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)などを傘下において、グループ一体運営を加速していくというメッセージになります。スタートアップ戦略部は、いわば、グループの司令塔の位置付けとなるのです」(塚原氏)
これまでもグループ各社でスタートアップ支援を推進し、互いに連携してきたわけだが、それでも互いの動きを新聞などで知ることがままあった。加えて、支援の打ち出し方も各社によって様相が異なっていた。やはりグループを上げてベクトルを合わせ、顔が見えるかたちで支援を行った方が、よりスタートアップとの親和性は高くなる。さらに世の中にMUFGの本気度を示せると判断した。
MUFGらしさを全面に出した4つの支援策とは?
塚原氏は麻布、渋谷の両支店長を経て、今回スタートアップ戦略部長に就任した。いずれの支店もスタートアップの集積地である六本木、渋谷エリアをカバーしており、塚原氏自身もスタートアップ経営者の事業戦略や資金繰りを直接サポートしてきた経験を持つ。
スタートアップ戦略部の陣容は約40名。拠点は東京のほか、名古屋、大阪にある。スタッフは、スタートアップへ直接支援を行う業務推進グループと、MUFG全体のスタートアップ支援に資するような施策の企画立案・推進を行う企画グループの2つに分かれ、フロント部隊となる20名強のスタートアップ営業部と共に活動を推進している。
「これまでは銀行が主体となっていましたが、これからは証券や信託、VCなどグループ各社のプロフェッショナルに出向してもらい、同じロケーションでやっていきたいと考えています。今後はもっとMUFGらしさを前面に出し、私達に期待されているところをより強化してきたいと思っています」(塚原氏)
このMUFGらしさとは一体何か。
1つ目がグローバル。日本から世界へ出ていくときに一番相談される金融機関になることだ。
2つ目は大企業とのコラボレーションだ。多くの大企業とのネットワークはMUFGの強みであり、オープンイノベーションをはじめ、大企業とスタートアップのコラボレーションについてさまざまな角度から支援を進めている。
3つ目がM&A。日本のスタートアップの7割の出口戦略はIPO(株式公開)だ。一方、アメリカのスタートアップの9割はM&Aとなる。むろんIPOをすることは起業家にとって1つの指標にはなっているが、日本では小粒で上場して、その後の成長加速が伴わない場合も多い。やはり世界で戦っていくためにはM&Aが必要になってくるという。
そして、4つ目が本丸とも言えるファイナンス、つまりデット(融資)だ。これを柔軟かつ大規模なものにしていく。これらすべてにエッジを効かせて、MUFGらしさを出していく方針だ。
生き残る起業家に必要なのは経営力とチーム力の2つ
では、足元のスタートアップの動向について、どう認識しているのだろうか。
「岸田政権が2022年に『スタートアップ育成5か年計画』を打ち出し、今後5年でスタートアップへの投資額を10倍に増やし、ユニコーン企業(※)を100社創出するという大きな目標を掲げています。しかし、2年経って足元を見ると、ユニコーン企業の数は横ばいで、投資額は微減となっています。ただ、アメリカと比べると、利上げやインフレの影響をあまり受けておらず、日本の状況はまだ悪くはない。規制改革も進んでおり、今後は巻き返していくと見ています」(塚原氏)
(※)評価額が10億ドル以上の非公開スタートアップ
とはいえ、日本でもスタートアップの二極化が進んでいる。優良と思われるスタートアップに資金が集中する一方、そうではないスタートアップは様子見される状況にある。しかし、起業家に対してはさまざまな補助金や支援策が打ち出されており、起業しやすい環境であることに変わりはない。
「日本から世界へ挑戦できるようなスタートアップを育成しようとすれば、ITデジタル系の相手は巨大IT企業群のGAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)になってしまいます。そこに勝つのはなかなか難しい。ならば、日本の勝ち筋はどこにあるのか。有望なのは大学の研究資産を活かした核融合などのディープテック系とみていますが、成長には時間もかかります。だからこそ、優秀な経営者の起用や大規模な支援が必要となっているのです。そこに私達もコミットしていきたいと考えています」(塚原氏)
日本でもかつてと比べれば起業したい若者は増えている。しかし、起業家を名乗っても経営者として生き残っていかなければ意味はない。支店長経験を持つ塚原氏は生き残る経営者の条件について次のように語る。
「ディープテック系は研究者出身も多く技術力が会社の存続を左右するのですが、ITデジタル系は経営者の力量が左右します。環境の変化に合わせて、事業内容も臨機応変に変えられる人。ビジネスモデルよりもその人個人にどれくらい経営力があるのか。また、資金調達を含めて、いかにチーム力があるのか。この2つがあって初めてやりたいことがやり切れるのです」
世界の知恵やイノベーションが集まってくる日本にしたい
実際、日本のスタートアップの課題は優秀な経営者の不足にある。支援者は多いものの、本格派のスタートアップ経営者はまだまだ少ない。また、日本のイノベーションといえば、これまでスタートアップよりも大企業のなかで生まれてきた経緯もある。今後スタートアップによるイノベーションの成功事例がもっと出てくれば、日本も変わると塚原氏は指摘する。
「日本の産業発展を加速させるには、日本初のスタートアップによる成功事例の創出をはじめ、スタートアップも含めて、世界の知恵やイノベーションが日本に集積していくというステップが重要だと思います。海外の人が日本で起業してもいい。日本は海外と比べて治安が良く、生活もしやすい。こうしたメリットを売りにして、優秀な人々を日本に呼び込むことも必要になっているのです」
さまざまな支援策を練っているMUFGスタートアップ戦略部。同部企画グループの木村 由佳氏、首代雅貴氏も「今年12月19~20日に東京・国際フォーラムでMUFGスタートアップサミットを開催します。大企業とのビジネスマッチングやスペシャルな講演も準備しています。最近はこうしたイベントも多いようですが、しっかりと皆さんに有用な価値を持って帰っていただけるようなイベントにしたいと考えています」と語る。
起業を目指す人向けに今年5月からスタートアップの成長に必要な支援サービスを網羅的に掲載した「MUFGスタートアップキット(https://www.bk.mufg.jp/houjin/lp/startup_kit/)」をリリース。同キットは、三菱UFJ銀行の口座を未開設または開設直後のスタートアップに対し、MUFG各社のスタートアップ向け決済・資金管理・株主管理サービスなどをWebページでワンストップ提供する内容だ。これまでMUFGは敷居が高いと思ってきた起業家には朗報かもしれない。起業家志望の皆さんも三菱という信用力をテコに一段高いステージに駆け上がってほしいものだ。

INTERVIEWEE

塚原 伸介 SHINSUKE TSUKAHARA
スタートアップ戦略部長
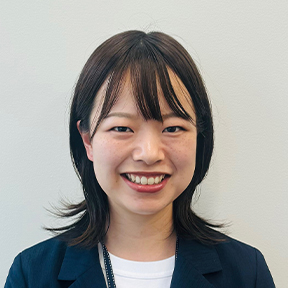
木村 由佳 YUKA KIMURA
スタートアップ戦略部 企画グループ

首代 雅貴 MASAKI SHUDAI
スタートアップ戦略部 企画グループ
株式会社三菱UFJ銀行
東京都千代田区丸の内1-4-5
1919年設立。資本金17,119億円。三菱UFJ銀行を含むMUFGグループは、「世界が進むチカラになる。」というパーパスを掲げ、日本発の総合金融グループとして、環境・社会課題に真摯に向き合い、その解決に全力で取り組みます。持続的な社会の実現のために、長い歴史の中で培ってきたプロフェッショナリズムをこれからも高め、拡げ続けます。東京・丸の内にある本館は現在建て替え中、2029年の竣工を目指します。



