
長崎の観光名所として有名なグラバー園。そこに立つと対岸には、三菱重工長崎造船所を望むことができる。初めてその景色を見たときは、長崎造船所の本館ビルに赤いスリーダイヤ、その下には修繕中の護衛艦があった。その光景は、まさに「三菱は国家なり」という言葉を彷彿とさせ、感動した思い出がある。

戦艦武蔵は、ここ三菱重工長崎造船所で1938年に起工された。言うまでもなく戦艦大和と並ぶ世界最大級の戦艦だ。当時、戦艦武蔵を建造することは軍事機密。そのため、船台を棕櫚(シュロ:ほうきなどに使用される素材)で覆い、建造の様子を周囲から見られないよう隠すことにした。棕櫚は一時市場から消えてしまうほど大量に集められた。吉村 昭の名作『戦艦武蔵』では、それがまるで事件の始まりかのように印象的な書き出しで始まる。
三菱重工長崎造船所は、もとは長崎鎔鉄所といわれ、江戸幕府がオランダから寄贈された蒸気船の修理工場として作られたものだ。幕府は横須賀造船所も建設し、明治に入ってから横須賀は海軍工廠となり、長崎は工部省所管の造船所となった。その後、明治政府は岩崎彌之助に長崎造船所を払い下げた。これ以降、民間造船所で三菱はトップの地位を築き、財閥形成を加速させ、時代のなかで台頭していく。
三菱重工長崎造船所の近代化に大きく寄与したのは、荘田平五郎だ。三菱全体を切り盛りする立場にありながら、長崎に駐在し、約5年間も所長として陣頭指揮をとった。今も残る洋館「占勝閣」は、もともと荘田の社宅として建てられたものだ。
近代の歴史がいっぱいつまった長崎造船所は、見ようによってはテーマパークのように映る。

旧木型場(史料館)
所内の占勝閣ほか、旧木型場(史料館)、英国製のジャイアント・カンチレバークレーン、第三船渠(ドック)は「明治日本の産業革命遺産」の構成資産に登録されている。訪問時は同社総務部の案内のもと見学したが、本当に見ごたえ十分。広大な造船所の敷地を回りながら、その規模の巨大さに気圧されるほどだった。造船所正門前の通りは、地元では三菱通りと称されており、長崎での三菱重工の存在感の大きさを示している。長崎に観光に来れば、長崎造船所は必ず目にする場所にあり、日本の近代史から見ても、この地の重要性を想像せずにはいられなくなる。そんな職場で働いているのはどんな人達なのだろう。
自分では到底買えない金額規模の注文を獲得したり
自ら折衝を行っていったりする醍醐味がある
150年以上の歴史があり、今も火力・地熱プラント、舶用機械、航空エンジン、防衛・宇宙機器の開発製造、高密度艤装船の設計などを手掛けている三菱重工長崎造船所。敷地面積約167万平方メートルのなかで、約3,500人の社員が働いている。

エナジードメイン スチームパワー事業部 営業部 海外営業3グループの杜 雨橋さんは、スチームパワー発電プラントのアフターサービスの海外営業を担当している。
「お客さまのニーズを把握し、技術部門と連携して提案や見積りをまとめ、契約交渉から締結後の製造~出荷後の請求までの一連の流れのなかで各種調整業務を対応しています」
杜さんはインド、パキスタン、バングラデシュ市場を担当し、大型案件の入札用書類の準備や見積り、お客さまとの予備品供給契約を締結する仕事などをこなす。
「やり甲斐は、かなりありますね。海外営業の仕事を長く続けていますが、常に新しい仕事を経験することができます。大規模な電力インフラに関わる製品であり、自分のお財布では、到底買えない金額規模の受注を獲得したり、各お客さまとの折衝を自ら行っていたりする醍醐味があり、かなり任せてもらっているなと感じています」
以前、杜さんが担当していた香港の大型案件ではお客さまの要求がとても厳しく、何度も交渉や社内稟議を進める必要があった。しかし、受注した際には、香港の夜景をつくる一助に自分も携わっている、そんな達成感を味わえたという。

三菱重工航空エンジン(MHIAEL)の長崎製造部 長崎製造課 工場管理係で働く疋田 智彦さんは、ベストセラー航空機Airbus社製A320neoに搭載されるPW1100G-JMエンジンの燃焼器、燃焼器ケースを製造している。
「工場管理係では建物や設備の導入~保守を担っており、そのなかでおもに建物とインフラを担当しています」
仕事のやり甲斐はどんなところにあるのだろうか。
「MHIAEL長崎工場は2020年に新設され、2024年に約2倍へ増築しましたが、製造するうえで求められる環境や最適な設備レイアウト、各種法令などを考慮しつつ予算や工程に収まるよう計画しました。工事による生産への影響を最小限にするよう配慮しながらの施工が必要であったため、幅広い知識とコミュニケーションが要求される仕事でした。毎日が勉強の連続であり、自分自身のスキルアップになったと実感しています。大規模な工事だったことから、社内外ともに調整すべきことが多くて大変でしたが、関係者一丸となって地図に残る仕事ができたことにやり甲斐を感じています」
総合研究所ターボ機械第一研究室の平戸 拓磨さんは、極低温流体(液体水素、液体窒素、LNG)、高圧ガス(圧力:1~90MPa)、回転機械に関する実験業務を担当している。製品としてはカーボンニュートラル製品(発電設備や燃料電池車)、宇宙機器などが対象となる。
「事業部や総研で開発した製品や部品の評価試験を担当しております。試験装置の設計、製作・手配、運転、データ整理まで、評価試験に必要な工程はひと通り行います。そのほかに実験棟設備の管理・保全作業も行っています」。
平戸さんは、世の中にまだない新製品を評価しなければならないため、難しい分、成功したときのやり甲斐は大きいという。
「ただし、事前に立てた工程通りに作業が進まないことが多く、多数のお客さまが見学に来ているなかでまったく装置が動かなかったこともあります。また、普段作業しないような場所(海外出張先など)で実験業務を行うと、慣れない土地なので作業効率が低下し、言語も文化も異なる外国の方とうまくコミュニケーションがとれずトラブルが多発するため、柔軟な対応が求められます。相手側がこちらの意図を理解してくれたときはうれしいですね」

大事なのはお客さまとの対話。トラブルでは
タイムリーな対応が求められ気が抜けない
調達部 長崎調達グループの松本 和寛さんはLNG燃料タンクに貯蔵されたLNGを気化、加熱、圧縮などの処理を行い、エンジンが必要とする圧力と温度に変換して供給するための、それぞれの役割を持つ装置・機器・計器・部品の調達業務(価格交渉、注文など)に従事している。
「三菱造船では、大型船舶におけるLNG燃料を安全かつ効率的にエンジンに供給するためのシステム(FGSS=Fuel Gas Supply System装置と呼ばれる)を開発し、国内の造船ヤードで建造される船舶へ同システムの販売と、高度な技術力を提供しています。LNG燃料は従来の重油燃料に比べ、CO2排出量等を大幅に削減でき、船舶業界でも環境負荷低減への取り組みは加速しています」
FGSSシステム用として調達した装置や機器などをモジュールに一体組みするが、それらを必要な時期にそろえるのがプロジェクト全体としてのマイルストーンになっている。各調達品においても各工場の生産工程との兼ね合いや出荷前検査などでの合否結果によって納期遅延が生じると、モジュールの組立工程に影響がおよぶ。
「昨年、モジュール納期が変更となった影響で生産能力を超過する事態が発生しました。1オーダー/月の能力値に対し、3オーダー/月の出荷が求められたためでした。その際、多数の取引先や社内関係部門と各種調整を重ね苦労しましたが、その後、調整した工程通りに出荷までこぎつけたときは、いつも以上に達成感を感じましたね」

三菱重工マリンマシナリ 舶用機械事業部 エネルギー環境機器営業課 アフターサービス第1チームの勝田 麻衣さんは、船舶用機械に関するアフターサービス提案を行っている。おもにタービン、引込式フィンスタビライザなどの製品を担当。定期ドックに合わせ、お客さまへメンテナンスの提案を実施するほか、顧客訪問やWEB会議の実施、受注や売上管理、分析などを担う。
「やはりやり甲斐は受注目標を達成することでしょうか。大事なのはお客さまとの対話だと思っています。でも、トラブルが起こったときはタイムリーな対応が求められるときもあり、気が抜けませんね」
難しい課題に対し知恵を出し合いながら試行錯誤
成果が出たときにはやり甲斐や達成感を感じる

艦船技術部の木村 太基さんは、護衛艦の艦内に搭載するシステムの設計を行っている。護衛艦にとって、どのようなシステムが必要なのか。客先である防衛省・自衛隊と調整し、具体的なシステムに落とし込んでいく業務を担っている。
「防衛省のある東京に出張する機会が多いですね。防衛省や自衛隊の方々と一緒に議論を重ねながら、システムを設計していくことは、苦労もありますが達成感もあります。防衛に直結する製品に携わっていますので、社会に貢献していることを、自分でも分かりやすいかたちで実感でき、やり甲斐につながっています」

総合研究所 化学研究部 化学第一研究室の池村 祐紀さんは、脱炭素化社会の実現に向けて、再生可能エネルギーを利用した水素製造技術のひとつである高温水蒸気電解(SOEC:Solid Oxide Electrolysis Cell)の開発に携わっている。SOECは高温高圧、高効率であることを特徴としており、逆反応であるSOFC(Solid Oxide Fuel Cell:固体酸化物燃料電池)としても利用できる。SOFCとは、高温で動作する燃料電池の一種で、燃料と酸素を化学反応させて、直接電気エネルギーに変換する装置。同社ではSOFCの技術実績があり、この技術をSOECに転用し、開発を推進している。
「近年では、CO2を利用したカーボンニュートラル燃料であるSAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空機燃料)の需要が拡大することが見込まれており、SOECを用いて水蒸気とCO2を一緒に電解するSOEC共電解の開発も実施しています。SOEC共電解にて得られた合成ガス(H2とCOを主成分とする)は、SAFを合成するための反応(FT合成反応)に使用されています」
具体的な仕事として、池村さんは高性能化に向けた新型SOECセルスタックの開発、共電解向けセルの開発では、ショートセルスタックを用いた試作(基体管の薄肉化、構成材料の改良)、物性評価、電解性能評価、分析、シミュレーションなどを行う。ちなみにセルスタックとは、セルと呼ばれる電解部が複数並んでいるもので、同社は円筒横縞型セルスタックを採用している。
「難しい課題に対して、当社にしかない技術や、知恵を出し合いながら試行錯誤を繰り返し、成果が出たときにやり甲斐や達成感を感じますね。また、社会問題となっている地球温暖化に対して、自分達が開発に携わった製品を通して脱炭素化社会へ貢献できるよう、今後も自分にできることを精一杯やりたいと思っています」。

杜 雨橋
UKYO MORI
エナジードメイン
スチームパワー事業部
営業部 海外営業3グループ

疋田 智彦
TOMOHIKO HIKITA
三菱重工航空エンジン
長崎製造部 長崎製造課 工場管理係
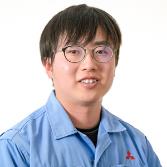
平戸 拓磨
TAKUMA HIRATO
総合研究所
ターボ機械第一研究室

松本 和寛
KAZUHIRO MATSUMOTO
三菱造船
調達部長崎調達グループ

勝田 麻衣
MAI KATSUDA
三菱重工マリンマシナリ
舶用機械事業部
エネルギー環境機器営業課
アフターサービス第1チーム

木村 太基
DAIKI KIMURA
艦船技術部
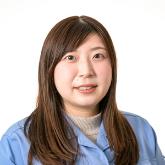
池村 祐紀
YUKI IKEMURA
総合研究所
化学研究部 化学第一研究室



