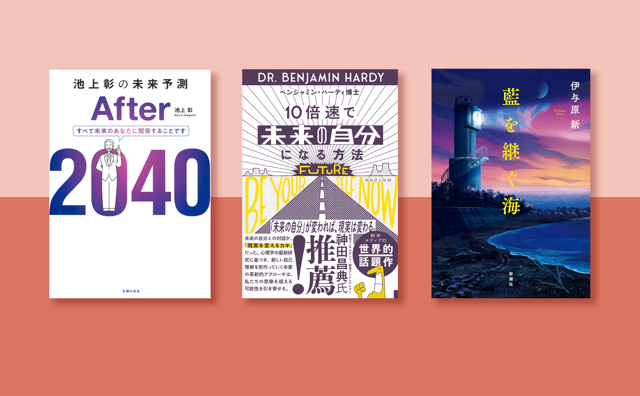
年明けに立てた今年の抱負、順調に達成しているだろうか。勢いがついてきた人、早くも中だるみしている人、壁にぶつかっている人などそれぞれだろう。年度替わりというもう一つの節目を前に、ちょっと俯瞰的に社会や自分自身を見つめ直し、新しい未来について考えてみるのもいいだろう。今回はさまざまな視点から未来について考える助けになる3冊をセレクトした。
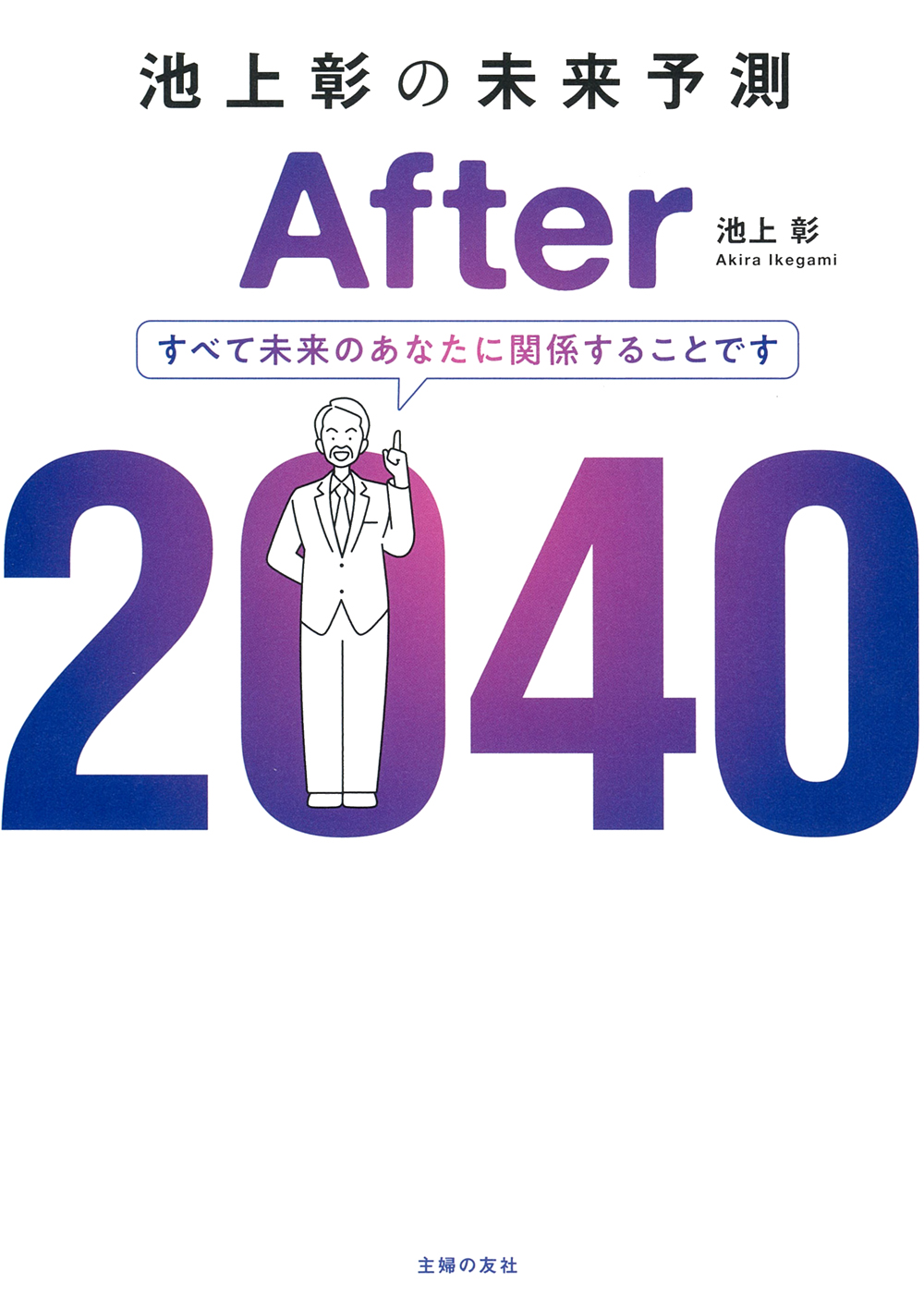
池上彰の未来予測 After 2040
池上彰著 主婦の友社(1,980円)
まずは社会の「未来」を知ることから。解説するのは池上彰さんゆえ、わかりやすいことは間違いなし。仕事、教育、自然災害、暮らし、健康という5つの分野で、16年後(本書発売は2024年夏なので、現時点からみると15年後)の2040年について考える。
16年前といえば、日本にiPhoneが本格上陸した時。ここから瞬く間に日本中にスマホが広がり、一般家庭での固定電話やファクス所有率が減少に転じ、さまざまなSNSが台頭し、電車に乗るのも決済処理も、ほとんどのことがスマホでできるようになった。社会の構造自体が大きく変わったと言える。つまり、この先の16年にも同じような変化が起きる可能性がある、と著者は語る。
AIによって仕事はどうなるのか、少子化、デジタル化で子どもの教育環境はどうなるのか、自然災害は増えるのか、女性の就労環境は変わるのか、感染症は広まるのか…。どのテーマも生活に密接に関わることながら未来が見えず不安が募っていることばかり。極端な悲観論や楽観論が世に流れるのも、そんな不安の表れだろう。そんな中、著者は落ち着いた語り口でその予測を語る。各章の締めくくりにはそれぞれ「明るい未来」と「暗い未来」を紹介している。その両方の図は、究極の状態を想像させてくれるとともに、「明るい未来に進むために私たちはどう考え、どう生きるべきか?」と考えさせられる。未来がどの方向に進むかを決めるのは、私たち自身なのだ。
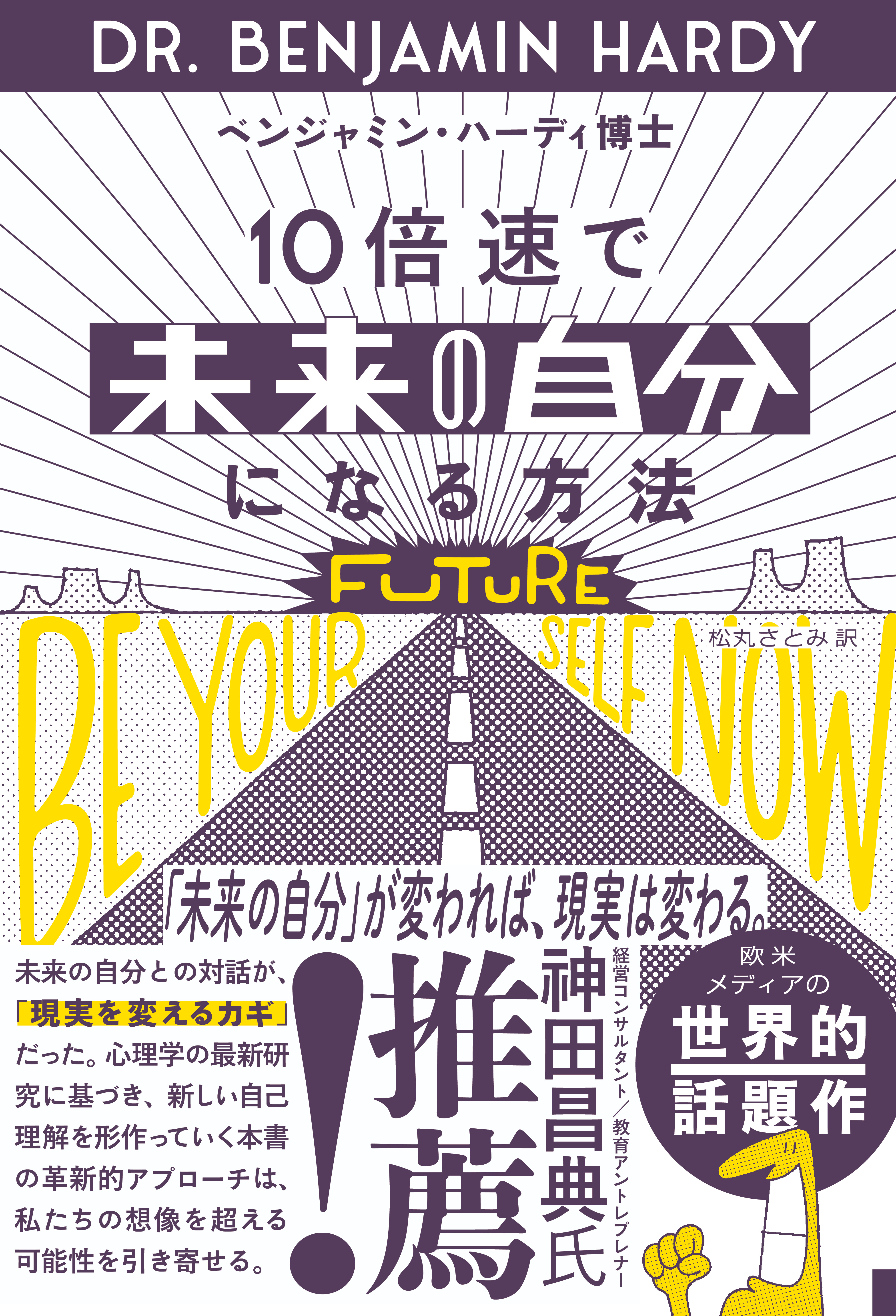
10倍速で「未来の自分」になる方法
ベンジャミン・ハーディ著、松丸さとみ訳
OEJ Books発行・めるくまーる発売(2,178円)
社会の「未来」について考えたあとは、その未来に向けてどう生きるべきか、自分自身の「未来」について考えよう。どんなキャリアプランやライフプランをもち、どんなふうに歩むべきか。本書では叶えたい未来に近づくための思考法が、多くの事例とともに綴られている。
私たちは日頃、これまでの経験、知見を活かしてどう成長していけるか、という「過去」の延長線上に自分の未来の目標や夢を描きがちではないだろうか。しかし本書では、過去を土台にした未来ではなく、未来の「ありたい自分の姿」を先に想像することを推奨している。現在の自分からは到底近づけないような絵空事に聞こえたとしても、むしろその方がより早く確実にその夢の実現に効果があるというのだ。
パート1では「未来の自分」になることを阻むものは何か、パート2では「未来の自分」とは何か、そしてパート3では「未来の自分」になるための7つのステップを提案。本文はイラストや太字などを交えてわかりやすく書かれているので、まずはパラパラとめくり、心に響いたコピーが目に飛び込んだら、そこから読み進めてもいいだろう。
具体的な「未来の自分」が見えたら、そこに近づくために何を優先すべきか、何を捨てるべきか、どんな投資をすべきかが明らかになる。迷った時、その答えはいつも「未来の自分」が教えてくれるのだ。人生の岐路に立ったときや、現状を踊り場と感じる人にぜひおすすめしたい一冊だ。

藍を継ぐ海
伊与原新著 新潮社(1,760円)
最後にご紹介するのは、もっとずっと大きな未来に思いを馳せたくなる一冊。第172回直木賞を受賞した話題の短編集だ。東京大学大学院で地球惑星物理学を専門に学び、その後富山大学で教授を務めていた著者の描き出す物語は、いずれも天文学や生物学、地質学を背景にしたミステリー仕立てのストーリー。徳島の小さな海岸、姫ヶ浦に祖父と住む中学生の沙月が、ウミガメの卵を孵化させ、一人で育てようとする、表題の「藍を継ぐ海」のほか、山口県・見島で萩焼に使われる伝説の土を探す謎の元カメラマンの男(「夢化けの島」)、都会から逃げるように移住した奈良の山奥で、ニホンオオカミと出会ったウェブデザイナー(「狼犬ダイアリー」)、北海道で年老いた父のために隕石を拾った場所を隠す妊婦(「星隕つ駅逓」)など全5編は、いずれも市井の人の小さなエピソードのようでありながら、日本各地の古くから根づく地理的、生物的な壮大な歴史を垣間見るようだ。
歴史は決して過去のものでなく今も脈々と続いていることを、科学を通して知らされると、それがそのまま未来にも繋がっていることに気づく。長い地球の歴史の片隅にいる私たちは、そこにどんな足跡を残せるのか。思わず空を見上げ、遠くを見つめたくなる。
ライタープロフィール

文/吉野ユリ子
1972年生まれ。企画制作会社・出版社を経てフリー。書評のほか、インタビュー、ライフスタイルなどをテーマにした編集・執筆、また企業や商品のブランディングライティングも行う。趣味はトライアスロン、朗読、物件探し。



