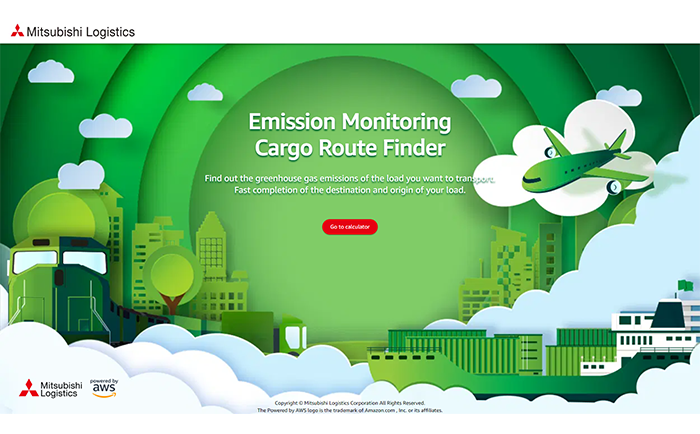アストモスエネルギーは、広島・因島の企業トロムソと資本業務提携を締結。気候変動対策のひとつとして独自のカーボンクレジット創出事業に本格的に参入し、東南アジア地域での拡大を目指す。
アストモスエネルギーは2024年1月、農畜産系残渣物を有価物(燃料、肥料、バイオマス原料等)にアップサイクルする機械を製造・販売している広島県因島市の企業、トロムソに出資。国内外においてカーボンクレジット創出および環境負荷低減に寄与する事業の立ち上げを目指し、資本業務提携を行ったと発表した。その背景について、アストモスエネルギーグリーン戦略室の東 洋子さんは次のように語る。
「世界で気候変動対策が本格化するなか、私達は低炭素であるLPガスそのものをよりグリーン化するためにバイオLPGに転換していくことを目指しています。しかし、それを今実現するには時間がかかるのも事実です。私達は、その過渡期として、カーボンクレジットを付加したLPガスをお届けすることが一つの策だと判断しました。そこを布石に時間を稼ぎながら、将来的にバイオLPGにつなげていきたいと考えているのです」
カーボンクレジットとは、温室効果ガスの排出量(カーボン)を排出権としてクレジット化することで排出削減量を企業間で売買し、排出削減枠によってオフセット(相殺)することができる仕組み。カーボンクレジットには、太陽光発電などによる再生可能エネルギーや森林管理によって二酸化炭素を吸収するクレジットなどがある。同社がカーボンクレジット創出事業に乗り出すのは今回の取り組みが初めて。そこでは農畜産系残渣物を扱うため、結果的にバイオLPGに近い領域となり、将来的にバイオLPGの素材となるものを探していくという狙いもある。
再利用が難しかったもみ殻をバイオマス化
今回、同社と資本業務提携したトロムソは、資源としての再利用が難しかったもみ殻を、因島の地場産業である造船の技術力を生かして、固形燃料に変える機械『グラインドミル』の製造を1994年に開始した企業だ。東さんは業務提携の理由をこう説明する。
「もみ殻の再利用が難しいのは、そのほとんどの成分がケイ素、つまりシリカであり、身近なものではスタッドレスタイヤなどに使用されています。タイヤに使われるように、それだけ地面をとらえるほど固くて強いという性質があります。そのため、もみ殻をすり潰すと機械の方が摩耗してしまうという難点があった。そんなもみ殻をバイオマス化する技術とともに、同社が持つ海外のネットワークや実証実験の成果を評価したのです」
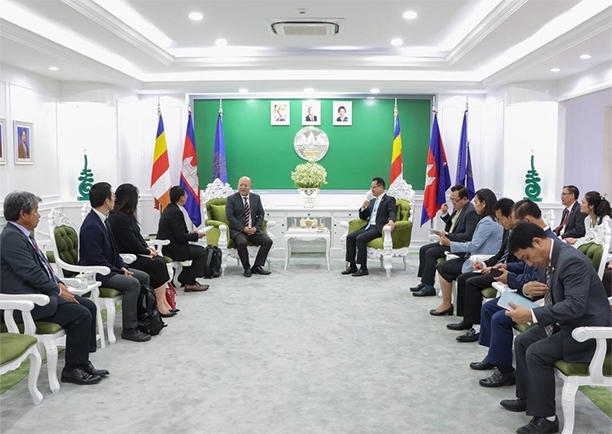
「カンボジア環境省との会談の様子」
トロムソは硬いもみ殻をすりつぶし固形化するだけでなく、バイオ炭や活性炭へと変化させるほか、浄水事業にも参画して最終製品の付加価値を向上させることに注力している。また、もみ殻にとどまらず、アーモンド殻や珈琲殻など地域ごとの残渣物を、有価物に変換することで、アフリカ、アジア、豪州など世界中で取り組みを広げており、広島県のユニコーン10への選出、COP28のジャパンパビリオンへの出展など因島から世界に向けて発信を続けている。
第1弾はカンボジア、同国の社会課題解決にも寄与
アストモスエネルギーでは、今回の資本業務提携を手掛かりにカンボジアでカーボンクレジット創出事業に着手していく方針だ。
「現在、カンボジアでは大量の薪が工場のボイラーに投入されているのが現状です。しかも雨季が長いため、含水率が非常に高い薪を使っており、燃焼効率もよくありません。こうした工場に固形化したもみ殻を代わりに使ってもらう。貴重な森林を伐採しないようにするところからスタートすることになります。ただ、バイオマスからバイオマスへの転換はクレジットとして難しい面もあり、ここをどう乗り越えていくかが最初の関門になると考えています」(東さん)
このほか、現地の市場調査や政府との交渉、NGOとの連携、サンプルテストなど今後3~5年かけて事業を軌道に乗せていきたいと東さんは語る。
「カンボジアの主力産業は衣服関連の縫製工場です。人手はかかりますが高い技術力を必要としない最終工程を担っています。問題は、そうした工場で使うアイロンのためにボイラーを利用し、大量の薪を燃やしているのです。日本企業もこうした工場を利用しています。カンボジアは現在、後発開発途上国(LDC)に指定されており、関税はありません。しかし、LDCからの卒業も促されているため、主力産業を活かしながら、どう低炭素化していくのかが課題となっています。雨季も長いため、太陽光発電に頼ることはできず、余分なコストもかけられない。政府でも悩んでいるところなのです」
将来的にカーボンクレジットを付加したLPガスを提供
こうした現地政府のニーズも捉えながら、アストモスエネルギーではカーボンクレジット創出事業に取り組むことになる。もともとエネルギー産業は、気候変動問題で矢面に立たされることが多いが、現在はどんな状況になっているのだろうか。
「欧州では一時、ガスボイラー全面禁止なども検討されましたが、それでは仕事がなくなる人達も多く出てくるため、各国も目標を下げ始めています。現在、欧州で行われる環境会議のテーマはバイオLPGなどの技術的なものがほとんど。先進国では低炭素化、バイオ化の動きが活発化する一方、発展途上国のほとんどは今も薪を利用しており、彼らがLPガスを使うだけでもかなりの低炭素化が進むといわれています」

現在、エネルギー業界でバイオLPGの生産はごくわずか。コストもかかるため、各社研究開発に努めているところだ。LPガスを化石由来ではないバイオマスなどの原料から合成するグリーン化を実現することはそう簡単ではない。
アストモスエネルギーでは、今回の資本業務提携を通じて、トロムソが得意とする農業残渣物のアップサイクル技術や新興国へのアクセスを通じて、カーボンクレジットを創出し、自社が販売するLPガスに付加していくことを目指す。東さんはこう語る。
「私達は今も低炭素の燃料としてLPガスを皆様に提供しています。これをよりグリーン化していくために、バイオ化、そして、カーボンクレジット創出の両面でチャレンジしていきたいと考えています。それと同時にカンボジアを始め、後進国の社会課題に貢献できる仕組みもつくっていきたい。私たちはこれからもインフラを担う縁の下の力持ちとして社会課題の解決に寄与していきたいと考えています」。
INTERVIEWEE

東 洋子 YOKO HIGASHI
グリーン戦略室
アストモスエネルギー株式会社
東京都千代田区丸の内1-7-12
1962年設立。出光興産(51%)、三菱商事(49%)が出資する合弁企業で、「液化石油ガス」(LPG=LPガス)の輸入、仕入、販売を手掛ける。従業員数324名、売上高6,736億円(いずれも2022年度)。LPガスは石油や天然ガスなどの化石エネルギーのなかで相対的に二酸化炭素排出量が少なく、燃焼時の排出ガスも極めてクリーンなエネルギーであるため、地球温暖化対策の即戦力としても期待される。